| 十月のやさい |
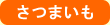
|
| ■五郎島金時 |
■みつき(安納こがね) |
|
|
|
|
|
| 加賀の伝統野菜。金沢市北部の砂丘地、五郎島育ちのさつまいもです。色も形も美しく、まるで和菓子のような上品な甘さ。“こぼこぼ”の食感が特徴です。「こぼこぼ」とは、金沢の方言で、「ホクホク」を意味します。
粉質ですが決してパサパサではなく、しっとり感もあります。焼き芋、レモン煮、スイートポテトなどにどうぞ。 |
|
| 種子島でしか作れない品種。「みつき」とは「蜜付き」の意味で、その名の通り非常に甘く、しっとりとした高品質のさつまいもです。焼き芋にするだけで、まるでスイートポテトを食べているかのよう。冷やして食べても美味。皮が白く、中身は鮮やかなオレンジ色をしています。このオレンジは、ニンジンなどに含まれるベータカロテンの色。 |
|
|
| ■黄金紫(こがねむらさき) |

|
果菜里屋が自信を持っておすすめする「黄金紫」は、鹿児島県種子島で古くから栽培されており、紫芋の中でも最も甘く、食味に優れているといわれる「紫7号」という品種です。生産量が少ないことから“幻のさつまいも”ともいわれています。外皮は灰白色、中身は穏やかな美しい紫色で、肉質は緻密でしっとり、品のよい甘さです。ポリフェノールを豊富に含み、特に女性に人気。天ぷら、蒸かしいも、焼きいも、アイスクリーム、和菓子などにどうぞ!
|
|
| ■パープルスイートロード |
■べにあずま |
|
|
|
|
|
| 焼き芋やふかし芋で食べてもおいしいと評価の高い、青果用に育成された新品種の紫芋です。千葉県産は「千葉紫」、茨城県産は「艶紫」の名で呼ばれることもあります。皮は暗紫色、中も見事な濃い紫色をしています。 |
|
| 千葉、茨城など関東を中心とした東日本で圧倒的な人気を誇ります。現在、日本で最も多く作られている品種です。皮は濃赤紫で、中身は黄色。食味のよいさつまいもで、焼き芋や菓子材料としてはもちろん、料理全般にむいています。 |
|
|
| ■鳴門金時/里むすめ |
皮の色が鮮やかで、食味のよい「鳴門金時」は、徳島県鳴門市の特産で、日本を代表する品種のひとつです。鳴門市は温暖で降雨量が少ない瀬戸内式気候にあり、水分の少ない砂質土壌で栽培されているため、水はけや通気性もよく、まさに“適地適作”。定期的に畑に海砂を入れ、海水に含まれるミネラルを根から吸収させることで、より味のいい鳴門金時を作り出しています。「里むすめ」は、その「鳴門金時」の厳選品。さつまいものトップブランドとして、全国にその名が知られています。
|

|
|
| ■太白 |
■七福人参 |
|
|
|
|
|
来歴不詳の在来種。戦前、戦後に関東で多く作られていたそうです。肉色は白。肉質は粘質で、甘味も風味も強いさつまいもです。
|
|
| 皮色は白、肉色はオレンジでベータカロチンを豊富に含んでいます。やや柔らかく、甘味のあるさつまいもで、てんぷら、コロッケ、蒸かしてポテトサラダ風に。 |
|
|
| ■おきこがね |
■べにまさり |
■しもん |
|
|
|
|
| 低デンプン性で、加熱しても甘みが増えないのが特徴。コロッケ、フレンチフライなど、ジャガイモを使う料理にお使いいただけます。 |
|
| 鮮やかな黄色い肉色で、肉質は強い粘質系です。糖度がかなり高いため、ねっとり感をいかし、きんとんのベースなどにむいています。 |
|
| ブラジル原産の野生の白甘藷(かんしょ)のこと。ビタミンEを通常のさつまいもの3.5倍含みます。漢方などに使用されています。 |
|
|
| ■栗まさり(神奈川県産) |
| 神奈川県のみで栽培されているさつまいもです。「栗まさり」の名前は、「栗にもまさるおいしさ」という意味を込めて名付けられたといいます。ぜひお試しください! |
|
| ■黄金千貫(こがねせんがん) |
| 鹿児島では主に焼酎の原料やデンプンとして広く使われている品種ですが、風味豊かなため、天ぷらや焼き芋などの食材としても親しまれています。中身も皮も白色。さまざまな料理に使える万能型です。 |
|
|
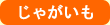 |
| ■インカのめざめ |
|
果肉はオレンジに近い濃い黄色で、調理後も鮮やかな色を保ちます。肉質は粉質と粘質の中間で、舌ざわりはごくなめらか。栗やナッツのようと形容されることもある独特の風味が特徴です。蒸すなどして、香りとホクホク感を生かした食べ方がオススメ。油で加工したときの褐変も少なく、フライドポテトなどにしてもおいしくいただけます。また、煮崩れしにくいので、煮込み料理にも適しています。
|
 ▲インカのめざめ
▲インカのめざめ |

▲中は鮮やかな濃黄色
|
|
| ■男爵 |
■キタアカリ |
■シャドークイーン |
|
|
|
|
| 明治末期に品種改良されて以来のロングセラー。中身は白色、肉質は粉質でホクホク感があります。コロッケ、サラダに最適。煮物にもむきますが、煮くずれします。 |
|
| 男爵を母に持つじゃがいも。中は黄色で甘みがあり、ホクホクした食感が絶品。粉ふきいも、ベークドポテト、サラダに最適。アルカリ食品でビタミンCやカロテンは男爵よりも多く含みます。
|
|
| 紫色の果肉が特徴の新品種。「キタムラサキ」や「インカパープル」より濃い紫色で、アントシアニン色素を約3倍含むといわれています。粘質系で、調理用。食味のよいじゃがいもです。 |
|
|
| ※ご紹介したじゃがいもは、いずれも北海道から産直できます! |
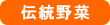 |
| ■山形県の伝統野菜各種 |
|
古くからその地方に伝わる伝統野菜の掘り起こしを積極的に推進している山形県には、魅力ある野菜が数多くあります。そのひとつが、「泉田さといも」。昔から「四ツ屋さといも」の名で親しまれてきたもので、クリーミーな口当たりが特徴です。「もってのほか」は、代表的な食用菊の一種。ピンクと紫色の混ざった色合いが美しく、料理の彩りに最適です。その他、ひと味違う「原木なめこ」もぜひお試しください!
|
 ▲泉田さといも
▲泉田さといも |

▲もってのほか
|
|
| ■飛騨高山の伝統野菜各種 |
 ▲すくなかぼちゃ
▲すくなかぼちゃ |
 ▲あきしまささげ
▲あきしまささげ |
岐阜県は飛騨の伝統野菜「すくなかぼちゃ」は、皮が薄く、栗のようにホクホクとして甘みがあり、舌触りが非常になめらかです。煮物や天ぷら、南蛮漬け、スープにどうぞ。「あきしまささげ」は、生では表面にしま模様がありますが、湯通しすると鮮やかな緑色に変化します。サヤには筋がなく、下ごしらえが簡単。和え物などに最適で、見た目も美しく仕上がります。また、サヤが太めなので、煮物に入れてもうまみを逃しません。
|
|
| |
|
◇◆◇◆◇◆◇◆ 新潟県長岡野菜の視察に行ってきました ◆◇◆◇◆◇◆◇
|
| 2009年9月25日~26日、「野菜と文化のフォーラム」主催の新潟県長岡野菜視察研修会に参加しました。旧長岡市内にて、大型で丸い「長岡巾着ナス」、香りの強い枝豆「肴豆」を視察。ピリッとした辛みがあるとうがらしの一種「かぐらなんばん」は、旧山古志村に古い種類が残っているとのことで、見学に行きました。翌日は、旧中之島町の「だるまれんこん」の圃場を視察しました。「だるまれんこん」は、10月下旬あたりから出回る晩生種のれんこんで、きめ細かくシャキシャキとした歯触りで定評がある長岡の伝統野菜です。中越地震から5年、各産地では、復興に向けて力強い取り組みが行われていました。 |
|
|
|
|
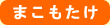 |
| ■まこもたけ(石川県産) |

|
「まこもたけ」という名前ですが、きのこの仲間ではなく、イネ科の多年草です。水稲のように水田で栽培され、若い茎が肥大した部分を収穫し、食用にします。旬は10~11月にかけて。低カロリーで食物繊維を豊富に含むヘルシー野菜です。淡泊な味でクセはなく、たけのこに似た歯触りが特徴。アクやえぐみがないので、生のままサラダにすれば、ほんのりとした甘みと独特の歯ごたえが楽しめます。ゆでる、蒸す、炒める、揚げる…など、加熱すると甘みが増し、よりいっそうおいしくいただけます。天ぷら、炒め物、和え物、煮物、炊き込みご飯の具、汁の実などにご活用ください。調理のコツは、加熱しすぎないこと。歯触りを残して仕上げるとよいでしょう。
|
|
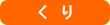
|
| 秋の到来を感じさせてくれるメニューといえば、「栗ごはん」ですね! 果菜里屋では、産地直送の新鮮な栗をみなさまにお届けいたします。いずれも高品質で食味のよい逸品です。栗ごはんだけでなく、渋皮煮や炒め物、デザートの素材としてもお使いいただけます。ちなみに、日本では、栗は縄文時代から重要な食べ物だったといわれています。栄養的には、ビタミンCやE、各種ミネラル、食物繊維などを豊富に含みます。栗のビタミンCはデンプンに包まれているため、加熱しても壊れにくいという特徴があります。栗の渋皮には、強い抗酸化作用がある成分が含まれています。渋皮煮は、理にかなった調理法なのですね。 |
| ■筑波(つくば) |
■銀寄(ぎんよせ) |
■利平(りへい) |
|
|
|
|
| 中生種。農林省農業技術研究所園芸部で、岸根X芳養玉(はやたま)を交雑した実生のひとつ。1959年に命名登録。栗需要期に収穫できる中生種では、最も優れており、全国で広く栽培。 |
|
| 中生種。果形は楕円形で、皮色は淡褐色。大阪府豊能郡能勢町原産の偶発実生。銀由、銀芳、銀吉、銀義などの異名があったが、大正2年の栗品評会で名称統一。 |
|
| 中・晩生種。楕円形で濃褐色。現在の岐阜県山県市に生まれた土田健吉氏が、1940年に中国産の栗とかけあわせて作ったといわれる。岐阜県で非常に人気のある栗。
|
|
| ■丹波(たんば) |
■石鎚(いしづち) |
■小布施(おぶせ) |
|
|
|
|
| 晩生種。京都丹波地区で生産。丹波栗は、日本書紀にも出てくるくらい、由緒正しい栗。品種はいろいろで、丹波で育てば「丹波栗」と呼ばれる。 |
|
晩生種。農林省園芸試験場で1950年に岸根X笠原早生を交雑した実生のひとつ。1968年命名登録。結実は良好で収量も多く、加工用品種としてもすぐれる。
|
|
小布施栗は600年の歴史があり、お米の代わりに「栗年貢」を納め、なかでも最上の栗は「御献上栗」として幕府に献上された、という話が伝わっている。
|
|
|
| ■その他 |
| 高知県・四万十産の「しまんと地栗」を使った、「地栗ペースト」(新鮮なしまんと地栗をペーストにしたもの。和洋菓子の材料などに)、「渋皮ドライ」(渋皮煮を乾燥させて食べやすいよう1個ずつパッケージしてあります)、「渋皮煮」(手間ひまかけてじっくり煮込んだ懐かしい味わいの渋皮煮です)もあります。「冷凍むき栗」(韓国産・中国産/LLサイズ)はすぐに使えて便利です! |
|
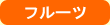 |
| この時期おすすめのフルーツは、柿「太秋(たいしゅう)」です。柿にもさまざまな品種がありますが、太秋は、現在出回っている柿のなかで最もおいしいといわれています。梨「あきづき」は、国立果樹研究所で「(新高×豊水)」×「幸水」を交配育成、平成13年に登録された品種で、果肉は緻密、ジューシーな味わいです。「さんたろう」は、「はつあき」と「スターキングデリシャス」を交雑して育成したりんごで、歯切れがよく生でもおいしいのですが、酸味がしっかりあるので、加熱調理にも向いています。その他、「極早生みかん」もお届けできます! |

▲柿「太秋」 |

▲梨「あきづき」 |

▲りんご「さんたろう」 |

▲極早生みかん |
|
|
| |
|
|